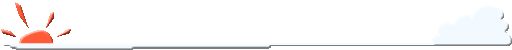
1.ケアプランに関連した制度等の主な流れ
●介護保険制度におけるケアプランに関連した制度等については、以下の大きな流れがあります。
①平成元年のゴールドプラン策定や、老人福祉法等関係8法の改正等、市町村を中心とした高齢者の介護サービスの整備と拡充の流れ。
②平成6年に国が監修し出版した「高齢者ケアプラン策定指針」(いわゆる入院・入所者用の「MDS-RAPs方式」)によって、全国の高齢者の医療・保健・福祉に係わる専門家や現場スタッフの関心が一気に「ケアプラン」に向けられた流れ。
③平成9年に介護保険法が制定され、介護支援専門員の試験や研修会も実施されると、ケアプランに関連した言葉(内容)が整理され、以前から呼ばれていたケアプランの「策定方式」は、「課題分析(アセスメント)」となり、介護サービス計画書については国が標準様式を提示した流れ。
④平成12年4月の介護保険制度のスタート前後になると、介護給付費の請求、特に居宅の場合については、「サービス利用票/別表」「サービス提供票/別表」「給付管理票」の作成といった極めて煩雑な給付管理業務に追われた流れ。
●つまり、一口に「ケアプラン」と言っても、介護保険制度を大きな流れの軸として、関連制度の検討と改正を伴い、さまざまな課題分析(アセスメント)の方式の開発や、新たな介護支援専門員と給付管理及び介護給付費請求等、事務・作業の内容と量は、煩雑・複雑化の道をたどりました。
●しかし、本来の「ケアプラン」は介護保険制度も「一つの社会資源」として活用し、高齢者の生活全般を支援する「適切で具体的なライフプラン」であることも、忘れてはならないことだと思います。