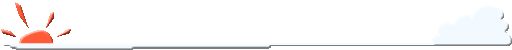
【1】ケアプランに関連した制度等の主な流れ
1.介護サービスの質と量の確保及び体制整備の時期
●昭和62年、福祉系の国家資格として「社会福祉及び介護福祉士法」が制定されました。
●平成元年になると、平成12年3月までの10年間の高齢者の介護サービスの具体的な整備計画であるゴールドプランが策定されました。
●平成2年には、市町村を中心とした居宅サービスを推進するための目的等で社会福祉関係八法が改正され、介護サービスの質と量の確保及び体制が整備されました。
2.ケアプランの開発と普及の時期
●平成4年には、高齢者のアセスメントからケアプランまでの基本的指針である高齢者ケアガイドラインが開発されました。
●平成6年には、国が監修した「高齢者ケアプラン策定指針」が出版されました。いわゆる入院・入所者用の「MDS−RAPs方式」のことです。
●これによって、全国の高齢者の医療・保健・福祉に係る専門家や現場スタッフ等の関心が一気に「ケアプラン」へと向けられました。
●また、各団体等でもさまざまな研修会等が積極的に実施されました。
●加えて、各団体等の独自の課題分析の方式の開発も進められました。
3.介護保険法の成立準備の時期
●介護保険法の成立を目指し、具体的な基盤整備が行なわれました。
●平成7年には、厚生省内に「老人保健福祉審議会」が設置され、新たな介護システム、つまり介護保険制度の必要性等の審議が開始されました。
●平成8年には、ケアサービス体制整備支援事業・モデル事業が実施され、現在の要介護認定調査の基礎作りも行なわれました。
●
また、平成9年には、介護支援専門員指導者養成研修会も開催されました。
4.介護保険制度の施行準備の時期
●いよいよ、平成9年に「介護保険法」が制定されました。
●平成10年には、「介護支援専門員標準テキスト」の出版、介護支援専門員実務研修受講試験も実施されました。
●そして、平成11年には、課題分析及び標準様式について通知も出されました。
●平成12年4月の介護保険法の施行を目指し、要介護認定調査、課題分析と介護サービス計画、サービス利用票等の作成等と、慌しい日が続きました。
5.介護保険制度の施行当初
●平成12年4月に介護保険制度がスタート。
●介護サービスの現場では、給付管理票や介護給付費の請求書の作成等の事務作業に追われる状況となりました。
●課題分析を伴うケアプランの作成より、国保連合会の審査(返戻や査定等)の結果に頭を悩まされた時期とも言えます。
6.現状と今後の展望
●介護保険制度がスタートして1年を過ぎ、当初に混乱していた介護現場での請求業務等も何とか落ち着いた状況となりました。
●しかし、平成14年の区分支給限度額限度額の一本化への対応という新たな課題等もあります。
●また、特に新規参入の民間事業所の深刻な「経営」の問題もあります。
●一方で、「適正なサービスの提供と質の向上」、そして「サービスの評価」という次の段階への課題の時期に入っています。
<2001年 2月 7日掲載>