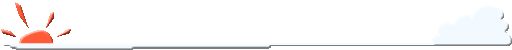
【2】課題分析(アセスメント)5方式の開発の経緯と特徴
1.MDS−HC/CAPs方式
●正式名称は、「在宅ケアアセスメントマニュアル」です。
●国際的な研究家と臨床家のグループ「InterRAI」(10数カ国20数名)によって、「MDS−RAPs」の在宅版として開発された方式です。
●状態の判断をする際の明確な期間を限定しており、記入はチェックやコード化方式を中心としている特徴があります。
●また、状態のアセスメント結果から導き出される、30種類の「領域」(トリガー)を設定し、問題の所在と原因、危険性等を探るためのガイドラインも提示しています。
2.日本訪問看護振興財団方式
●正式名称は、「日本版成人・高齢者用アセスメントとケアプラン」です。
●日本訪問看護振興財団によって高齢者訪問看護アセスメント用紙と「MDS-RAPs」双方を実践例に基づき比較検証し、両者の統合版として開発された方式です。
●「MDS−HC/CAPs」方式と同様、30種類の「領域」を設定し、より広範囲な課題分析できます。
●また、課題分析の記入用紙は、複数回にわたって記入できる方式になっています。
3.三団体ケアプラン策定研究会方式
●正式名称は、「包括的自立支援プログラム」です。
●全国老人保健施設協会、全国老人福祉施設協議会、介護力強化病院連絡協議会の3団体のケアプラン合同勉強会である三団体ケアプラン策定研究会において開発された方式です。
●他の方式と異なり、要介護者等の課題分析からではなく、提供されている介護や用具等の検討・分析をするケアチェック表を中心にしていることが特徴です。
●また、状態調査に関しては、国の要介護認定の調査票を使用しています。
4.日本社会福祉士会方式
●正式名称は、「ケアプラン実践記録様式」です。
●日本社会福祉士会の「ケアマネジメント研究会」において、国内外のアセスメント票の収集及び検討、ケアマネジメント事例収集の結果を踏まえて開発された方式です。
●課題分析の内容は、在宅における生活全般にわたって最も広範囲、詳細となっています。
●生活の全体性、個別性、継続性、地域性という4つの観点で捉えられる生活ニーズの分析を行うことや、課題分析や介護サービス計画を含めたケアマネジメント(介護支援)の方式としての特徴があります。
5.日本介護福祉士会方式
●正式名称は、「生活7領域から考える自立支援アセスメント・ケアプラン」です。
●日本介護福祉士会の「ケアマネジメント研究会」において、自立支援アセスメント・ケアプラン方式として開発された方式です。
●当初は、ホームヘルプサービスにおいて使用されていたものが、その後、施設・在宅現場での実践と検討を重ねて開発されたものです。
●衣、食、住、体の健康、心の健康、家族関係、社会関係の「生活7領域」からとらえた生活援助を基礎とした課題分析が特徴となっています。
<2001年 2月 7日掲載>