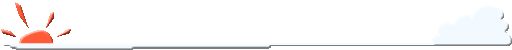
【3】神戸市開催による「こうべケアマネジャーセミナー&感謝の夕べ」のセミナー要旨
演題:「楽は苦の種、苦は楽の種! ~ケアマネ一喜一憂~」
2001年9月13日(木)に神戸市主催により新神戸オリエンタルホテルにて開催された上記のセミナーで行なった記念講演の要旨です。参加者は約600人でした。
1.介護保険制度への期待と現実
●介護保険制度は、高齢社会の到来にともない、介護の重度化や長期化、家庭介護の低下、従来の医療・保健・福祉等の制度の総合化等を目的として、医療、年金、労働(雇用・労災)につぐ新たな社会保険として創設されました。制度の創設にあたって、介護支援専門員の皆様の期待としては、利用者本位による介護サービスの選択や、市区町村を中心とした地域に密着した介護サービス提供、そして民間企業等の多様な事業者の参入という規制緩和等によって健全な介護サービスの市場が形成され、そして皆様の専門性と役割への大きな期待、その責任(使命)に胸を膨らませておられたことでしょう。
●しかし、実際に制度が施行すると、医療・保健・福祉の専門家であり、介護支援専門員の皆様の日常業務は、要介護認定調査や介護サービス計画書及びサービス利用票の作成とサービス提供票の交付、給付管理票の作成等の事務作業の煩雑さに追われ、当初思い描かれていたケアマネジメントとは大きく異なる現実に思い悩まれていることと思います。また、多忙な業務によって、いわゆる「燃え尽き症候群」となる可能性も高い状況だとも思います。
●そこで、もう一度、介護保険制度の創設に至る時代の大きな流れ(経緯)を振り返ることによって、制度本来の目的と特性、そして今後の展開(方向性)について考えてみたいと思います。その大きな流れの中で、高齢者やご家族、そして職場や関係機関の「仲間達」との日々の細かな関わりを思い浮かべ、医療・保健・福祉等の専門家の皆さんや先輩方の歩んできた道、汗と涙で積み上げてきた「今」を再確認することで、また「明日」の笑顔での活力となることを願います。
2.介護保険制度創設への経緯
(1)戦後の社会保障制度形成の時期
●終戦の昭和20年から約7年間続いたGHQによる占領下の間に、生活保護法や社会福祉事業法の制定、そして昭和25年の社会保障審議会の勧告等、現在の日本の社会保障制度の骨格ができあがった時期でした。
(2)高度成長期と社会保障制度拡大の時期
●昭和30年頃より日本は好景気を迎え、昭和36年には所得倍増計画が閣議決定される等、その高度経済成長等を背景として、昭和36年には国民皆保険・年金が実現し、また、昭和38年には老人福祉法、昭和39年の母子福祉法の制定によって、戦後約20年間かかって「福祉6法」体制が確立した時期です。
●昭和45年には高齢化率が7%を超え、日本は高齢化社会に突入し、同年には社会福祉施設緊急整備5ヵ年計画が策定され、一気に特別養護老人ホームを中心とした施設整備が進みました。
●その一方で、急激な高度経済成長は、産業構造や国民の生活、家族の形態をも大きく変化させ、公害という大きな社会問題も起きた時期でもありました。
(3)福祉見直し論と日本型福祉社会構想の時期
●70歳以上の医療費無料化等、社会保障費が飛躍的に増大した昭和48年は「福祉元年」と宣言されましたが、その年の秋にはオイルショックが訪れ、突然に高度経済成長は終焉を迎え、経済的問題と目前に迫る高齢社会の到来(平成6年に高齢化率14%となりました)も含め、厳しい「福祉見直し論」が論じられ、新経済7か年計画の中で、「新しい日本型福祉社会の創造」の構想が決められ、日本は欧米型の福祉国家の道ではなく、家族が介護を中心的に担う道を選んだわけです。
●昭和56年から第二次臨時行政調査会が開始され、老人医療費や福祉施設利用料の一部負担化、そして老人保健法の制定等、激動と「大きな選択」をした時期だったといえます。
(4)介護サービスの体制整備の時期
●国鉄分割・民営化によってJRが発足した昭和62年には、社会福祉士及び介護福祉法が制定され、また老人保健法の改正によって老人保健施設も創設されました。
●平成元年になると、消費税の導入に伴いゴールドプランが策定され、10年間の具体的な達成目標の設定と、施設入所から在宅福祉中心主義への明確な転換が行われ、翌年には老人福祉法等8法が改正され、戦後の社会福祉における歴史的な大改革が行われました。
●また、在宅介護支援センターや老人訪問看護制度の創設や、訪問介護等の在宅3本柱の推進によって、市町村を中心とした在宅サービスが飛躍的に拡充した時期でした。
(5)ケアプランの開発と普及の時期
●平成6年には、厚生省に高齢者介護対策本部が設置され、「高齢者介護自立支援システム研修会」の創設等、「新たな高齢者介護の仕組み」の実現化が急ピッチに進められました。
●平成4年から開発とその有効性が検証されていた高齢者ケアガイドラインは、平成6年に「高齢者ケアプラン策定指針」として出版され、現在の各課題分析手法の開発と研修等、高齢者の医療・保健・福祉現場は「ケアプラン一色」に染まった時期でした。
(6)介護保険法の成立のための準備の時期
●平成7年になると老人保健福祉審議会が設置され、介護保険制度の成立がさらに具体化して行きました。特に大きな論議(課題)は、要介護認定の方法でしたが、さまざまな論議の末、現在の要介護認定の仕組みが採用され「ケアサービス体制整備支援モデル事業」により、ケアプラン及びケアマネジメントの試行も全国で行われた時期でした。
●そして、白熱した論議ののち平成9年12月に介護保険法が成立しました。
(7)介護保険法の施行準備の時期
●介護保険法が制定された翌年の平成10年には「介護支援専門員標準テキスト」が出版され、介護支援専門員実務研修受講試験が開始されました。
●平成11年には要介護認定が開始し、課題分析及び標準様式(介護サービス計画書)についての通知も出され、給付管理業務等の提示も行われ、介護支援専門員の期待と不安、そして使命感に胸が膨らんだ時期でした。
(8)介護保険法の施行当初
●平成12年4月の介護保険法施行直前まで制度の不明確な内容が多々あり、またサービス利用票の作成等の給付管理及び請求業務等の事務作業の煩雑さと理解不足に加え、法施行直前に訪問介護の複合型の追加や、短期入所の拡大や振替措置、第1号被保険者の保険料徴収の先送り等があり、介護現場は混乱が続き、長年論じ、蓄積されてきたケアマネジメントや、高齢者サービス調整チームとして定着していたケアカンファレンス(サービス担当者会議)等も十分に実施できない現状のようです。
3.介護保険制度の最近の動きと今後の展望
(1)訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化
●来年の平成14年1月から訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化が実施されます。サービス利用票や給付管理票等の様式の変更だけではなく、国保連合会のセンターシステムや各事業所のシステムの変更という大きな課題もあります。
●平成13年12月以前の請求に関しては現行の様式によること等、介護現場の混乱が心配されます。
(2)介護サービスの質の向上への取り組み
●介護サービスの質の向上に関しては、きわめて重要な課題ですが、実現にはかなりの時間と努力が必要です。
●具体的な取り組みや課題としては、①訪問介護の適正化、②身体拘束ゼロ作戦、③介護サービスの評価事業、④指導・監査の徹底、⑤利用者からの苦情への対応、⑥介護相談員派遣等です。
(3)介護支援専門員に対する支援体制の強化
●介護保険制度の根幹を担い、利用者と制度を直接に橋渡しするキーパーソンである介護支援専門員の皆様への支援については、制度自体を左右する大きな課題ですから、以下のような支援体制等が進んでいます。
①介護支援専門員支援会議(国及び都道府県)の開催
②ケアプラン指導研修チームの設置と派遣
③介護支援専門員の養成研修の推進
④地域ケア会議の設置
⑤介護支援専門員相談窓口の設置
⑥介護支援専門員活動促進モデル事業
⑦介護支援専門員の業務実態調査
(4)介護保険制度の見直し等
●介護保険制度は施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものと定められています。現在、要介護認定や、介護報酬等の見直しのための調査・研究や検討等が行われています。
●しかし、介護保険制度は、社会保障制度に限らず、社会全体の大きな構造改革の流れの中にある「一つの柱」あるいは「大きな変化の序章」とも考えられますので、社会全体をとらえる広い視野と長期的展望において判断されるべきだと思います。
4.介護支援専門員への期待と課題
●介護支援専門員の役割とその重責については前述のとおりで、課題分析による介護サービス計画の作成と、サービス担当者会議の開催、サービス利用の連絡調整、モニタリング及び評価等のケアマネジメントの他に、居宅においては給付管理業務、そして委託された場合の介護認定調査等がありますが、それらの業務の適正・標準化が急務だと思われます。
●特にサービス担当者会議(地域ケア会議)の開催と、モニタリング及び評価の実施については、基本的な考え方にとどまらず、具体的な方法の開発が強く望まれます。また、それを介護現場で実現するためには、介護支援専門員への体系的で継続的な研修とサポートが必須であると思います。
●一方、煩雑で多忙な日々を過ごされている皆様だからこそ、あえて、介護保険制度は、あくまでも社会資源の1つであり、高齢者を支援するメンバー(チーム)は、家族を中心に、介護支援専門員だけでなく、在宅介護支援センターや医療・保健・福祉・行政等のフォーマルサービス、民生委員やボランティア等のインフォーマルサービスを総合的に、しかも新たなサービスや「人」をつくりだして行くという、皆様の各専門分野の「初心」にたちかえり、地域でのネットワークづくりが重要であることを再確認することが必要だと思います。
●つまり、地域全体に目を向ければ、「仲間が一杯!」だということです。「楽は苦の種、苦は楽の種」であり、その種を地域にまき続け、地域にしっかりとした根をはりめぐらせた花と実を育てて行くことが大切なことではないでしょうか。
<2001年 9月13日掲載>