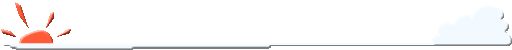
【4】介護保険制度における介護支援サービスについて
1.介護支援サービスとは
●介護保険制度における「介護支援サービス」とは何でしょうか。「介護支援専門員基本テキスト(全3巻)」((財)長寿社会開発センター発行)では以下のように説明されています。
「介護保険制度においては、保険給付の対象者である要介護者および要支援者(以下要介護者等)という」に対し、個々の解決すべき課題(ニーズ)や状態に即した利用者本位の介護サービスが適切かつ効果的に提供されるよう、多様なサービス提供主体による保健・医療・福祉にわたるケアの各サービスが総合的、一体的、効率的に提供されるサービス体系を確立することとしている。このためのサービス提供の手法がケアマネジメントであり、介護保険制度における『介護支援サービス』である。」
●つまり、「介護支援サービス」を理解する場合、整理すると以下のキーワードが重要なポイントとなります。
①解決すべき課題(ニーズ)
②状態に即した利用者本位の介護サービス
③適切かつ効果的に提供
④多様なサービス提供主体
⑤保健・医療・福祉にわたるケアの各サービス
⑥総合的、一体的、効率的に提供
⑦サービス体系を確立
⑧サービス提供の手法
●以上のキーワードを見てどう思われますか。「なるほど」「そうか」「そのとおり」「当然のこと」などの意見が多いと思います。どれひとつとして、異論がない、理想的な項目です。
●しかし、もう一度、ゆっくり、しかも具体的に考えてみてください。「介護支援サービス」は、「理念」とか「考え方」などではなく、あくまでも「手法」なのです。しかも、介護支援専門員の方々にとっては「実務」なのです。
●つまり、例えばキーワード③の「適切」と「不適切」の明確な違いが分かりますか。明確に他者に伝えられますか。「こんな感じ」「こんな視点」「このような考え方」などでは「手法」になりません。いつ、誰が、何を、どのように・・・など(5W2Hなど)を明確にです。そして、もし100人の介護支援専門員の方々が、ある介護サービスの提供などについて「適切かどうか」(適切さ)を判断した場合、全員が同じ結果にならなければなりません。
●どうでしょうか。難しいですね。結論から言うと、介護保険制度における「介護支援サービス」については「仕組み」は導入されていますが、その「手法」については、まだ確立されていないと考えられます。
●その「仕組み」については、できるだけ専門性や客観性を高めるために、「介護支援専門員」という専門職をつくり、「課題分析(アセスメント)」の手法の活用、そしてチームケアや独断(独善)性の回避も目的としてた「サービス担当者会議」(ケアカンファレンス)などがあります。
●さらに言えば、「サービス担当者会議」(ケアカンファレンス)で、「この計画は適切(不適切)だ!」と判断する場合でも、参加者の各人の「専門性」に依存するしかないというのが現状です。
●もちろん、私も「明確な答え」を持っているわけではありません。しかし、いくつかの手法などの研究や開発を続けており、研修会(演習)で実際に提案(検証)を続けています。
2.介護支援サービスの過程
●介護支援サービスの過程については、「介護支援専門員基本テキスト(全3巻)」((財)長寿社会開発センター発行)では以下のように説明されています。
①サービス利用者である要介護者等の生活全般の解決すべき課題(ニーズ)を明らかにする「課題分析(アセスメント)」の段階
②課題分析で明らかにされたニーズを解決するための総合的な「介護サービス計画(ケアプラン)」の作成の段階
③介護サービス計画に組み込まれた各種サービスを実施するためのサービス種類やサービス頻度・内容等に関する「サービス事業者等との調整・仲介(施設の場合はサービススタッフとの調整が主)」の段階
④計画に沿って実施される「サービスの継続的な把握(モニタリング)・サービスの評価」の段階
●この介護支援サービスの過程の中で、最も重要で、最も難しいのが④のモニタリングと評価だと思います。前述の「適切さ」が難しい理由もここにあります。
●つまり、「評価」の明確な手法や基準(物差し)が確立されていないのです。最近、第三者評価事業など、サービスの評価についての論議や具体的な取り組みが進んでいますが、いわゆる「総論賛成、各論反対」という状況がしばらくは続くと思います。
●なぜなら、介護現場のスタッフの方々は実感されていると思いますが、介護サービスに「絶対はない!」ということです。専門性や立場の違い、利用者の意向の「揺れ動き」、時間の変化、そして最終的には価値観や人生観等の違いなどが根底にあるからです。
●私の考えは、全く逆転の発想です。それらを根底にするから答えが見つからないと思うのです。そのことについては、前述の私が行なっている研修会(演習)で実際に提案(検証)していることや、今後このホームページ上でも説明して行きたいと思います。そして、皆様と一緒に考えて行きたいと思っております。
3.介護支援サービスのあり方
●介護支援サービスのあり方については、「介護支援専門員基本テキスト(全3巻)」((財)長寿社会開発センター発行)では以下のように説明されています。
①高齢者介護に対する社会的支援
②高齢者自身による選択
③在宅介護の重視
④予防・リハビリテーションの充実
⑤総合的、一体的、効率的なサービスの提供
⑥市民の幅広い参加と民間活力の活用
⑦社会連帯による支え合い
⑧安定的かつ効率的な事業運営と地域性の配慮
●この介護支援サービスのあり方は、どれも重要な事柄で、介護保険制度の目的や理念そのものです。私としては掲示板でも書いたとおり、特に「⑦社会連帯による支え合い」を忘れてはならないということがポイントだと思います。
●「介護保険制度だけでは支えきれない」「介護保険制度への不満」等が中心的な論議になるのではなく、「介護保険制度は社会資源のひとつ」という基本を忘れず、インフォーマルサービス(支援)も含む全ての社会資源をフル活用することが重要であり、その方法が「ケアマネジメント」なのです。
●そのためには、地域でのネットワークづくり(地域組織化)が絶対条件です。
4.介護支援サービスの基本的理念と意義等
●介護支援サービスの基本的理念と意義等については、「介護支援専門員基本テキスト(全3巻)」((財)長寿社会開発センター発行)では以下のように説明されています。
①要介護者等とその世帯の主体性尊重の仕組み
②自立支援、多様な生活を支えるサービスの視点
③家族(介護者)への支援の必要性
④保健・医療・福祉サービスを統合したサービス調整の視点
⑤サービスの展開におけるチームアプローチの視点
⑥適切なサービス利用(効果性、効率性)の視点
⑦保健・医療・福祉サービス(保険給付サービス等)とインフォーマルサポートを統合する社会資源調整の視点
●この介護支援サービスの基本的理念と意義等は、前述の総括的な内容です。重複したような内容ですが、だからこそ「頭の中に焼きつけておく」必要があるとも言えます。
●ただし、言葉としては「美しい」文章ですが、実際に実行しようとすると難しいと思います。前述の理由もありますし、介護支援専門員の方々にとっては、「時間が足りない」「職場(事業所・法人・会社等)で働く職員・社員としての立場」等、現実は厳しいですね。私も介護現場に長年働いておりましたので、よく分かっているつもりです。
●一般的に人は川の流れに逆らって上流に上って行くのはとても辛く、その努力を続けることは至難の技です。流れに身をまかせて下流に行くことの方が簡単で、一般的だと思います。もっと言えば、何もしなければ流されるということです。
●ひとりでは大変でも、仲間がいれば頑張れるし、仲間としっかりと手をつないで一緒に頑張れば何倍もの「大きな力」となり、流されにくいと私は信じています。
<2001年10月28日掲載>