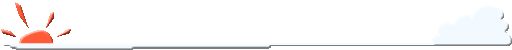
【5】介護保険制度における介護支援専門員の役割と重要性について
1.介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
●介護保険制度における「介護支援専門員(ケアマネジャー)」とは何をする方(職種)でしょうか。「介護支援専門員基本テキスト(全3巻)」((財)長寿社会開発センター発行)では以下のように説明されています。
「介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行なう者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める者をいう。」
●つまり、前回の「【004】介護保険制度における介護支援サービスについて」で説明している「介護支援サービス」を行なう者であり、政令で定められた「専門家」だと言えます。
●また、キーサードとしては、以下のポイントが重要となります。
①要介護者等からの相談に応じる
②心身の状況等に応じた適切な介護サービスを利用できるようにする
③関係機関との連絡調整を行なう
④自立した日常生活を営むのに必要な援助を行なう
⑤専門的知識及び技術を有する者
⑥政令で定められた者
●以上のキーワードから、前回説明した「介護支援」と同様、相談や連絡調整、自立への援助等を行なう具体的な「手法」を行なう専門知識と技術をもつ「実務者」ということです。
●つまり、相談援助、心身状況等に応じたサービス利用援助、連絡調整、自立への援助等を適切に行なう必要があるわけです。
●それでは、それらの方法は体系的に確立されているでしょうか。介護支援専門員は全員がそれらの方法を適切に行なえるのでしょうか。しかも、体系的に確立されているということは、例えば同じ心身状態の要介護者等に対しては、同じ適切な方法が行なわれるのかということです。もちろん、画一的な対応という意味ではありません。
●視点を変えて考えれば、それらの方法は、介護支援専門員である前に、保健・医療・福祉等の専門職であり、対人援助等の方法は適切に行なえることが前提となるのでしょう。
●しかし、現場にいらっしゃる介護支援専門員の方としては、基本的な考え方や視点等は共通認識はあるものの、実際の方法については、習熟のための努力と検討、そしてその苦労を続けられていることと思います。
●私の現場での経験から言えば、「現場は絶えず動いている」「答えは机の上ではなく現場にある」と声を大にして訴えたいと思います。
2.介護支援専門員の業務
●介護支援専門員の業務については、「介護支援専門員基本テキスト(全3巻)」((財)長寿社会開発センター発行)では以下のように説明されています。
①要介護認定に関する業務
②介護支援サービスに関する業務
③居宅サービスの上限管理等に関する給付管理の業務
●つまり、介護保険制度の根幹である要介護認定、介護サービスの計画と連絡調整、限度額管理という業務を担う重要な役割であり、本来、「保険者」が行なう業務であるともいえます。
●また、要介護認定調査を実施しているときの介護支援専門員は、いわゆる「見なし公務員」となりますので注意が必要です。
●居宅においては、上限管理等に関する給付管理業務と請求業務の負担が予想以上に大きく、「時間が足りない」という現場の声が多く聞かれます。
●本来は、介護支援サービスに関する業務が中心であるべきで、現場でもその「歯がゆさ」に苦悩している日々で、「燃え尽き症候群」となった方々も少なくないようです。
3.介護支援専門員の基本姿勢(基本倫理と基本視点)
●介護支援専門員の基本姿勢(基本倫理)については、「介護支援専門員基本テキスト(全3巻)」((財)長寿社会開発センター発行)では以下のように説明されています。
①人権尊重
②主体性の尊重
③公平性
④中立性
⑤社会的責任
⑥個人情報の保護
●また、介護支援専門員の基本姿勢(基本視点)については、「介護支援専門員基本テキスト(全3巻)」((財)長寿社会開発センター発行)では以下のように説明されています。
①自立支援
②ノーマライゼーションとクオリティ・オブ・ライフ
③生涯発達
●以上の基本倫理と基本視点という介護支援専門員の基本姿勢については、どれひとつとして忘れてはならないことで、絶えず、何度も繰り返し自己確認する必要があります。
●特に、基本視点の自立支援や生涯発達等については、「介護を行なう側」と「介護を受ける側」、そして「介護してあげる」と「介護してもらう」という関係(考え)にならないようにする必要があります。つまり、全ての要介護者等に対して、人格、人権の尊重の精神を忘れてはならないということです。
●しかし、介護支援専門員も「生身の人間」です。「聖人君子」でもありません。日常の業務の多忙さや職場の環境等で、ストレス状態となり、「つい」不適切な言動を行なう場合も否定できません。
●支援(援助)する介護支援専門員の心身の健康と、「職場の健康」が大事だと思います。
4.介護支援専門員の役割と機能
●介護支援専門員の役割と機能については、「介護支援専門員基本テキスト(全3巻)」((財)長寿社会開発センター発行)では以下のように説明されています。
①利用者本位の徹底
②チームアプローチの実施(総合的判断と協働)
③居宅サービス計画に基づくサービス実施状況のモニタリングと計画修正
④サービス実施体制におけるマネジメントの情報提供と秘密保持
⑤信頼関係の構築
⑥社会資源の開発
●以上の中で、一般的に重要なポイントとして言われているのは、「①利用者本位の徹底」についてだと思いますが、現在の現場での課題は、「②チームアプローチの実施」である介護サービス担当者会議や地域ケア会議(ケアカンファレンス)が開催できないことや、「③居宅サービス計画に基づくサービス実施状況のモニタリングと計画修正」ではないでしょうか。
●特に、介護支援サービスの中で重要なモニタリングが十分に行なわれていないことは、国としても重要課題として考えられており、介護サービスの適正化事業や、介護支援専門員の支援事業等が急激にすすめられています。
●また、「⑥社会資源の開発」については、発想の転換と、地域でのネットワーク、行動力等が必要になります。つまり、「介護保険制度だけでは支えられない」と言う不満から発想を転換し、介護保険制度を社会資源のひとつとして考えた上で、「他に利用できるサービスはないか」「なければどうやったらできるのか」「そのために自分は何をすべきか」等です。
●この新たな社会資源を開発したり、発想の転換をするためには、介護支援専門員だけではなく、関係者皆での「仲間づくり」が重要だと思います。
<2001年11月 5日掲載>