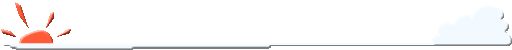
【6】介護サービスの特性について
1.有形財(モノ)ではないという特性
●介護サービスは、サービス提供者の行為そのものであり、いわゆる形がある「モノ」ではないという「非有形財」という特性をもっています。
●具体的には以下のような非有形財の特性があります。
①介護提供者の行為そのもの
②利用前に目で見たり、試したりできない
③生産と消費が時間・場所的に切り離せない
④再現することができない等
●つまり、例えばパソコンならば、見ることもできるし、実際に触って使うこともでき、そして、在庫管理(倉庫等に買い置きすること)もできます。
●しかし、介護サービスは、実際に利用を「試す」ことはできず、利用そのものになってしまいますし、例えば「今日は、明日の分まで排尿介助しておきます」などが絶対にできません。
●また、人間の行為そのものですから、時間を止めることはできず、過去の行為(時間も含めて)を全く同じに繰り返すことはできません。それが再現性がないということです。
2.評価することが難しいという特性
●介護サービスの上記の特性があるため、評価することも難しくなります。
●一口に評価と言っても、主観的評価と客観的評価、数量的評価と質的評価等、その評価の尺度、基準は様々です。
また、主観的評価と言っても、誰の主観なのかが問題であり、利用者自身の評価としても十分な知識(単純な良し悪しでさえ判断が難しい)が必要ですし、本来「人の気持ちと状況は絶えず変化する」ものです。
●つまり、以下のようなことがあるため、介護サービスの評価は極めて難しいと思われます。
①実施や内容の確認及び評価が難しい
②評価の尺度が多様で確立されていない
●しかし、介護サービスの評価が難しいからといって、「評価できない」「評価しない」というわけではありません。
●介護保険制度においては、評価の基準や仕組みは整備されています。
●先ず、評価の仕組みとしては、利用者の心身や社会的状況に合致した適切な介護サービスを判断、つまり評価する役割として介護支援専門員という専門職を整備しています。さらに、ひとりの介護支援専門員が判断(評価)しないようにサービス担当者会議という仕組みも用意されています。
●次に、介護サービスが適切かどうかの「基準」として、提供事業者の指定基準があります。建物の広さや設備等のハード面と人員配置のソフト面での基準です。この基準を満たさなければ、指定違反や減額査定等のペナルティーがかせられるわけです。
●また、介護サービスの提供前に、その提供内容について文書による契約を行ない、その契約どおりに行なったかどうかの、いわゆる実績評価の仕組みもあります。
●そうです。この実績評価の仕組みこそが介護サービス計画、ケアプランなのです。
●ですから、計画はなぜ作成するのかと言えば、「評価」するためと言っても過言ではなく、特に形がない(モノではない)特性と持つ介護サービスにおいては、この「事前の文書による契約」が重要となるのです。
3.同じ行為でも費用が違うという特性
●また、介護サービスは同じサービス、ケアであっても費用が違うという特性もあります。
ただ、この点に関しては、他のホテル等のサービスの場合も同じで、今までの「措置」の時代よりも「一般の市場」に近づいたと言えると思います。
●しかし、他のホテル等のサービスと違って、利用者がその費用の違いが分かりにくいのではないでしょうか。
●極端な例ですが、最近建設されたばかりの最新設備で部屋も広い入所施設と、数十年前に建設された古く部屋も狭い入所施設を比較した場合、普通に考えれば前者が「高い」はずですが、実際には、その建物の新しさや設備面と費用は関係ないわけです。
●また、極めて高い質のサービスを提供しても費用の違いには反映しません。
●以下の点等によって費用が異なります。つまり、介護報酬額を算定するサービスコードの違いによって費用が決まるわけです。
①時間数によって違う
②時間帯によって違う
③人数によって違う
④提供者の資格によって違う
⑤提供事業所によって違う等
<2001年11月12日掲載>