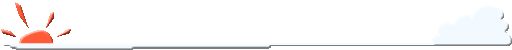
【7】介護サービスの理解の難しさについて
1.介護サービスの特性による理解の難しさ
●介護サービスについては、前回の「【6】介護サービスの特性について」で説明した以下の特性があり、そのために評価等の以前に、理解すること自体が難しいわけです。
●言いかえれば、理解すること自体が難しいということは、その介護サービスを文書による計画、つまり介護サービス計画(ケアプラン)の作成と、モニタリング及び評価がきわめて難しいことは当然のことと思います。
●また、保健・医療・福祉の専門家である介護支援専門員の方々などにも理解が難しいことが、介護サービスの利用者である高齢者やご家族が理解することの難しさはあえて言う必要がないと思います。
①有形財(モノ)ではないという特性
②評価することが難しいという特性
③同じ行為でも費用が違うという特性
2.介護サービスと用語等の理解の難しさ
(1)ケアマネジメントに関連した用語
●以下に「ケアマネジメント」に関連した用語の一例を列挙しました。
●どうでしょうか。全て「正確に」理解されていますでしょうか。また、全ての用語の違いが正確に、しかも具体的に「この部分が違う」等というような理解がされているでしょうか。
●とても難しいことだと思います。ただし、ここで言いたいこと(主旨)、重要なポイント)は、専門用語とは言っても、あくまでも「基礎的な用語」であるにもかかわらず、それが介護支援専門員という専門家の方々の中でも共通理解や共通認識されていないという現状自体が問題だということです。
●その現状を、単に「勉強不足だから」という一言では解決できないし、解決できることではないと思います。
●つまり、いかにこの介護サービスというものの理解が難しく、これから具体的な方法論も含めて体系化され、確立化されて行くことが急務だと思います。
●もちろん、大学等の先生方や研究者の方々にとっては、既に確立していることだと思われるかもしれませんが、介護保険制度自体が「成長の過程」にある中において、現場の介護支援専門員の方々の現状としては、「正確な理解は難しい」と言えると思います。
①介護支援サービス
②居宅介護支援サービス
③ケアマネジメント
④ケースマネジメント
⑤サービス調整(コーディネーション)
⑥給付管理業務
(2)ケアプランに関連した用語
●次に、ケアプランに関連した用語を以下に列挙しました。
●上で列挙したケアマネジメントに関連した用語とは違い「同様のもの」と「過程のひとつのもの」等が混在しています。
●例えば、介護保険制度における「居宅サービス計画」と「施設サービス計画」の役割等の違いや、具体的に作成する場合の違い等について、正確に理解できているかということです。
①課題分析
②アセスメント
③ケアプラン
④介護サービス計画
⑤居宅サービス計画
⑥施設サービス計画
⑦個別援助(介護)計画
⑧その他の様々な計画
(3)介護サービスに関連した用語(食事を例にして)
●今度は、食事を例にして「介護サービス」に関連した用語を以下に列挙しました。
●介護サービス計画だけでなく、日常的に使用される言葉です。つまり、介護支援専門員の方々だけではなく、サービス提供者である各事業所の方々、そして介護サービスの利用者である高齢者とご家族などが、以下の言葉に対して共通理解、共通認識ができるでしょうか。
●ある方にとって「食事のお世話」と言ったら、食材の買い物から始まり、調理や配膳、そして片付けまでを含み、別の方にとっては、「摂取介助」を意味しているかもしれません。
●つまり、この共通理解、共通認識を得ることが最重要で、関係者間での誤解が生じないように、介護サービスを利用(提供)する場合、「事前に、文書で、契約する」という3つの条件が必要になるわけです。
●そうです。それが介護サービス計画書(ケアプラン)の本質であり、最重要な役割だということです。
●なお、このことは私の約10年前から変わらず主張してきたことです。
①食事のお世話
②食事の介護
③食事の介助
④食事のケア
⑤食事のサービス
3.介護サービスの費用の理解の難しさについて
(1)地域区分と一単位の単価の違い
●介護保険では、介護サービスを利用する事業所の所在地によって単位の単価が以下のとおりに異なっています。
●ある利用者のお住まいの場所が、その地域区分の境界付近にあれば、同じサービスを利用して、単位数が同じであっても実際の計算では金額が異なることに対して、理解や納得をすることが容易なことでしょうか。
●介護報酬請求の仕組みについて、一般の利用者の方に説明し、納得を得ることの難しさは、現場の介護支援専門員の方々は痛感されているのではないでしょうか。
①特別区(東京都特別区 ) :10.48円(10.72円)
②特甲地(大阪府大阪市等):10.40円(10.60円)
③甲地(福岡県福岡市等 ) :10.24円(10.36円)
④乙地(北海道札幌市等 ) :10.12円(10.18円)
⑤その他(その他の地域 ) :10.00円
(2)居宅における区分支給限度額
●居宅における区分支給限度額についても、上と同様に利用者の方に説明をし、納得していただくことが難しいと思います。
●また、訪問通所区分は月で管理し、短期入所は認定有効期間で限度額を管理するという仕組みは、さらに理解を難しくしています。
●しかし、平成14年1月1日からの区分支給限度額の一本化については、限度額の管理としては考えやすくはなりますが、現場の介護支援専門員の方々にとっては、この変更について、再度、利用者への説明と納得を得るという「難題」が課せられたわけです。
①要支援 : 6,150単位(訪問通所)/ 7日(短期入所)
②要介護1:16,580単位(訪問通所)/14日(短期入所)
③要介護2:19,480単位(訪問通所)/14日(短期入所)
④要介護3:26,750単位(訪問通所)/21日(短期入所)
⑤要介護4:30,600単位(訪問通所)/21日(短期入所)
⑥要介護5:35,830単位(訪問通所)/42日(短期入所)
(3)居宅における支給限度額管理
●居宅における支給限度額管理は、上の区分支給限度額の管理だけでなく、以下の管理もあります。
●しかも、例えば③居宅介護(支援)住宅改修費支給限度基準額については、区分支給限度額のように月や認定有効期間で管理するわけではないという、理解するには複雑な仕組みとなっています。
①居宅介護(支援)サービス費区分支給限度基準額
②居宅介護(支援)福祉用具購入費支給限度基準額
③居宅介護(支援)住宅改修費支給限度基準額
④種類支給限度基準額
⑤経過的居宅給付支給限度基準額
(4)介護サービス費用にかかわる利用者負担額計算
●さらに、いわゆる利用者の方が「結局、私はいくら払えばいいの?」という質問に答えるためには、以下の加減算(足し算や引き算)などが必要になります。
●どうでしょうか。現場の介護支援専門員の方々の日頃のご苦労のほんの一部ですが、この介護サービスの理解の難しさと、それを利用者の方に説明し、納得を得ることの難しさが再認識できましたでしょうか。
①介護サービス費用の加算や割引
・特別地域加算
・送迎加算等の付加的な加算
・初期加算等の限定的な加算
・料金の割引
・人員欠如等による減額
②利用者の負担額の計算
・介護保険対象分の利用者負担
・介護保険対象外の利用者負担
・食材料費等の実費負担
③給付・減免・減額等
・介護保険の給付
・介護保険優先公費の給付
・高額介護サービス費の適用
・社会福祉法人の減免
・その他の利用者負担軽減措置
<2001年11月24日掲載>