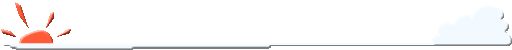
【9】不適切な介護サービスを提供しないためには
1.適切な介護サービスと不適切な介護サービス
●介護支援サービス(ケアマネジメント)の基本的な考え方として、高齢者の状況に即した適切な介護サービスの提供ということが重要だということと、その「適切さ」を判断することや実現することの難しさについては、「【4】介護保険制度における介護支援サービスについて」等で説明しましたが、ここのでは逆に「不適切な介護サービス」を提供しないためにはどうすれば良いのかということについて説明しています。
●介護サービスを提供する側(者)にとっても、介護サービスの「適切さ」よりも、「不適切さ」の方が比較的に考えやすいのではないでしょうか。
●サービス担当者会議(ケアカンファレンス)においても、課題(ニーズ)の捉え方や、援助目標、サービスの内容等についての実際に論議されるのは、「適切さ」ではなく「不適切さ」がないかどうかが多いと思います。
●つまり、「このケアプランについて何かありませんか」という問いの「何か」というのは、利用者等の状況への質問を除けば、「問題はないか」ということでしょう。
●介護サービスの特性から言っても、実際には「もっと(更に)適切な」という検討は、「終わり無き」、「答え無き」、「永遠に続く」検討でもあります。
●もちろん、「もっと(更に)適切な介護サービスはないか」という積極的な論議は、本来目指さなければならないことです。
●利用者にとっても、「適切かどうか」ということは判断は、主観的にも難しいことですが、「不適切かどうか」ということ、つまり、「望ましくない」ことは、判断するというより「嫌だ」という「感情」となって認識できます。いわゆるクレームです。
●また、上で説明したとおり、「適切さ」には終わりも無く、答えも無く、そして利用者自身が判断することも難しい状況から考えると、利用者にとっては「適切さ」への評価よりも、「不適切さ」への批判(クレーム)の方が考えやすい環境にあると言えます。
●それでは、その不適切な介護サービスを提供しないためには、どうしたら良いのでしょうか。以下(次項)に説明して行きます。
2.不適切な介護サービスが提供されない環境をつくる
●不適切な介護サービスを提供しないためには、先ず「提供されない環境づくり」が最も重要なことになります。
●不適切な介護サービスを「提供しない」ではなく、「提供されない」ということが、ここでの大きなポイントになります。
●介護サービスとは人間の行為そのものですから、介護サービスを提供する者の知識や技術に左右されることは言うまでもありません。
●それ以上に、提供者の意識や倫理観等の方による影響が重要だと思います。どんなに高い知識や技術をもっている専門家でも、いわゆるモチベーションが下がったら、「適切」や「不適切」以前の話しとなってしまいます。
●もちろん、精神面だけが充実すれば良いという極論もナンセンスな話しです。
●不適切な介護サービスが提供されない環境とは、提供者の意識や倫理観等を高められる、あるいは下がらないための「働きやすい職場づくり」が必要で、経営者の努力は当然ですが、提供者自信も仲間作りやストレスの発散、自己達成等の自助努力も必要となります。
●また、専門家としての知識や技術を習熟するためには「体系的」で「継続的」な研修が必要です。前述のとおり、答えも、終わりも無い介護サービスの適切さを目指すには、提供者の資質向上(スキルアップ)も永遠に続ける必要があるということです。
●ただし、「習うより慣れろ」「先輩の後姿を見て学べ」「技は人から盗め」等や、「経験と勘」という昔ながらの研修体質では、資質向上に時間がかかり過ぎますし、「ブレ」が大き過ぎます。そこで、「体系的」で「継続的」な研修が必要だと強調したわけです。
●さらに、不適切な介護サービスが提供されないためにはチェック体制が必要です。チェックは「気づいた時」に「気づいた人」が「気づいた方法」で等では、ほとんど効果はありません。
●チェックは、時(タイミング)や、人、方法、そして問題があった場合の対処の内容まで決めておく必要があります。そして、継続することが重要です。
●チェックには、内部チェック機能と外部チェック機能があります。つまり、提供者自身や施設(事業所)内での自己チェックと、行政の指導監査やオンブズマン、第三者評価等の他者チェックの2種類があり、全てが重要です。
●しかし、いわゆる「人の粗さがし」や「人の批判」という方向になる傾向がありますので、注意する必要があります。そうなると、最初に説明したように、最も重要な提供者のモチベーションが下がることになり、「本末転倒」の結果になってしまいます。
3.不適切な介護サービスを提供しない計画を作成する
●前述の環境づくりに加え、利用者個人ごとに不適切な介護サービスを提供しないためには、ケアプランが重要になります。
●ケアプランの中で標準様式の「居宅サービス計画書(2)」の「サービスの内容」に、「訪問介護」等のサービスの種類だけや、「食事の介護」等の「ケア項目」だけを記述しているものを見ることが少なくありませんが、この「不適切な介護サービスを提供しない」ための計画としては、更に追加の記述が必要となります。
●つまり、「必ず○○○する」や「絶対に○○○しない」、あるいは「○○○の場合は○○○する(しない)」といった内容も必要だということです。
●実際には、介護サービスを提供しない居宅の介護支援専門員の方々が作成する居宅介護サービス計画書の場合、「居宅サービス計画書(2)」への記述が難しければ、「居宅サービス計画書(1)」の「総合的援助の方針」の欄には記述すべきだと思います。
●例えば、入浴することを目的として通所介護(デイサービス)を利用している場合、朝の迎えに行った時に体調を確認し、もし体調が思わしくないようであれば、「今日はデイサービスセンターに着いて血圧等を測定し、入浴できないことも考えられますが、利用されますか?」というというような確認が行なわれる計画(ケアプラン)が作成された場合と、そうでない場合を考えると、利用者からのクレームやトラブルは未然に防げる可能性が高いのではないでしょうか。
●また、健康や医療面においての「不適切さ」は、取り返しのつかないことになる危険性もあるので、この面においても主治医をはじめ、保健・医療と福祉の連携は絶対に怠ってはなりません。
4.介護サービス提供後のサポートを欠かさない
●例えば、購入した自動車等や、形のない「生命保険」等であっても、「アフターフォロー」が顧客満足度に大きな影響を与えます。
●それが、利用者自身が適切さを判断することが難しい介護サービスの場合は、更にこのアフターフォロー、サポートが重要になります。
●つまり、モニタリングと評価の重要性です。そのため、私(管理者)は、主にこのケアプランのモニタリングと評価の重要性についての講義や演習を行なっているわけです。
●介護だけでなく、形がない全てのサービスは、「利用してみなければ分からない」「別なサービスと比較してみなければ分からない」のです。ですから、何度も説明しますが、介護サービスを利用後の利用者の状況を確認することが大切なのです。
●また、「気づいた時」にとか、「最初だけ」ではなく、継続的に行なうことが必要です。
●そのため、介護保険制度におけるモニタリングは、「介護サービスの継続的な把握と連絡調整」として重要な過程、役割としてとらえられています。
5.クレーム(苦情)対応の仕組みをつくる
●利用者のクレーム(苦情)については、前回講座の「【8】利用者が望む介護サービスについて」で説明をしましので、ここでは対応の仕組みづくりの重要性についてのみ説明します。
●利用者のクレームは「出さない」ことが最も重要であることは、今まで「不適切な介護サービスを提供しない」ということで説明してきました。
●しかし、利用者がクレームを「出せない」「言えない」状況や、「言ってもどうにもならない」という「諦め」の状況となってしまうのは、絶対に避けなければなりません。
●そういう状況になっていないか。利用者が自由に希望やクレーム等が言える状況かどうかを、常に自問自答する環境でなければならないと思います。
●次に、利用者からクレームを受けた場合は、「即時」に「誠心誠意」で対応する必要があり、もし解決するのに時間がかかるのであれば、その進捗状況を逐次報告、説明することも誠意の表れとして、利用者からは逆に評価される結果となります。
●また、クレームや何らかの問題が生じた場合、「人」や「環境」等が原因とは考えず、必ず「過程」(プロセス)に問題があると考えてください。
●「あの人の対応が悪い」「この職員の人数では無理」等の発想は棄ててください。
●介護サービスの提供者や提供(対応)方法に問題があれば、「人のせい」ではなく、研修体制の充実と、業務のチェック体制の改善の方向で考えてください。そうしなければ、根本的な改善にはなりません。
●そうです。これが最初に説明した「不適切な介護サービスが提供されない環境をつくる」ことなのです。「人のせい」にすると、組織の改善ではなく、人のモチベーションの低下により、どんどん「改悪」して行くという悪循環に陥ってしまいます。
●つまり、ケアプランも含めて以下のキーワードを忘れないでください。と考えてください。
「解決しなければならない問題(課題)は、人ではなく過程(プロセス)や仕組み(方法)にある!」
<2002年 1月 2日掲載>