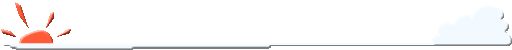
�y�P�O�z���T�[�r�X�ɂ�����i���Ǘ��̏d�v���ɂ���
�P�D���T�[�r�X�ɂ�����i���Ǘ��̏d�v��
���O��́u�y�X�z�s�K�ȉ��T�[�r�X����Ȃ����߂ɂ́v�Ɋ֘A�������Ƃł�����A���T�[�r�X�ɂ�����i���Ǘ��̍l������A�������邽�߂̕��@�i�Ή��j���ɂ��Đ������܂��B
�����̕i���Ǘ��ɂ��ẮA�P�A�v�������l����ꍇ�ɂ����Ă��A�u���̂��߂̌v�悩�v�u�����v�悷��̂��v�u�ǂ��������e���v��i�L�q�j����̂��v���A��{�I�ȋ^��ɑ��铚���̂ЂƂƂ��āA�ƂĂ��d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ�܂��B
���������A��쌻��̕��X�ɂƂ��ẮA�u�i���v�Ƃ������t���̂��̂��A������u�����Ȃ�Ȃ��v�u��a��������v�ȂǂƎv����������Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���܂��A���̕i���Ǘ��Ƃ����l������A���̗l�X�ȕ��@�Ȃǂɂ��ė�������̂͑�ςɓ�����e�ł���Ǝv���܂��B�����ŁA�����ł͊ȒP�ȓ��e�ɂƂǂ߁A�ڂ������e�́u�P�A�v�������ʍu���v�Ő������܂��B
���ŏ��ɑO��Ƃ��āA���T�[�r�X�́u�i���v�ł͂Ȃ��̂Łu�i���Ǘ��v�Ƃ͊W���Ȃ��Ǝv������������邩������܂���B���T�[�r�X�͊m���Ɂu�`�����镨�v�ł͂���܂��A�u�i�v�ł��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��A�Ⴆ�A�i������̂��߂ɍ��ꂽ�h�r�n�i���ەW�����@�\�^���ۓ���K�i�j�́u�h�r�n�X�O�O�P�v���擾����Ă�����ʗ{��V�l�z�[�������N�O���炠��A���̉��ی����x�n�݂��@�Ɏ擾���ꂽ�i�擾���j�{�݂��������Ă���悤�ł��B
���܂��A��쌻��̕��X���u�i���v�Ƃ����ƁA���x�������Ă���u�K���v�Ƃ��A�u�㎿���v�u���x���v���Ƃ�������⊴�o�ōl������ꍇ�������悤�Ɏv���܂��B
���Ⴆ�A�����ԂŌ����u�����v�u�R��̗ǂ��v�u���S�n�̗ǂ��v�����i����\�킷�������A���T�[�r�X�Ǝ��Ă���Ǝv����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���������A������x�ǂ��l���Ă݂Ă��������B�u�����v�u�R��̗ǂ��v�u���S�n�̗ǂ��v���́A�����Ԃ̃��[�J�[�A�^�����ł̔�r�̖��ł����āA�S�������^����N���̎����Ԃɂ����Ĕ�r����邱�Ƃ͂���ł��傤���B
���܂�A���������ԂȂ̂ɁA�F�B�����������̂͑����̂ɁA���������������̂͒x�����Ƃ������u������O��v�͊�{�I�ɂ͂Ȃ��͂��ł��B������������A���ɃN���[���A���ւ��̑Ώۂł��B
���������i�́A�u�ǂ��Ŕ����Ă��v�u�������Ă��v�u�N�������Ă��v�����i���Ȃ̂ł��B���̕i����ۏi�i���ۏj���邱�Ƃ��i���Ǘ��̑�ςɏd�v�ȖړI�Ȃ̂ł��B
�����T�[�r�X���u�҂ɂ���āv�u�@�ւɂ���āv�u����ꏊ�ɂ���āv�u���鎞�ɂ���āv���A�u������O��v�������邱�Ƃ͋�����邱�Ƃł��傤���B�v�́A���T�[�r�X�͗��p�҂��Ƃ́u�ʐ��v�ł����āA�ґ��̓s���ɂ���ĉ��T�[�r�X�̎�ނ�A���Ɨʓ��Ɂu�o���c�L�v�������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA���ꂱ�����P�A�v�����̊�{�I�ȍl�������Ǝv���܂��B
���������A�i���́u�o���c�L�v�������Ƃ��d�v���Ƃ����Ă��A���T�[�r�X���u���I�v�ł����Ă͂����܂��A���p�҂̏��ɑ������u�Ջ@���ρv�ȑΉ��͕K�v�Ȃ��Ƃ͓��R�ł��B
���O�q�̎����Ԃ̗�́A�u���i�̐M�����v�ł���A������u���T�[�r�X�̐M�����v�Ƒ�����A���T�[�r�X�ɂ�����i���Ǘ��������ɏd�v���Ƃ������Ƃ��������Ă���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����́A�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ����̊�{�I�ȍl�����Ƃ���10�N�ȏ�O���猾�������Ă��܂������A�P�A�̕i�����Ǘ�������@�Ƃ��āA�F�X�ȃP�A�̃��j���[�\��`�F�b�N�\�A�}�j���A�������쐬���A���̑��̕��@�����s������J��Ԃ��Ă��܂����B�ŏ��̍��͈���I�ȋ����ᔻ���܂����B�������A���ی����x�n�݂��_�c����鍠�ɂȂ�Ƒ����̕��X�̗�����悤�ɂȂ�A���ی����x�n�݂ɂ�芔����Г��̉c���c�̂��Q������悤�ɂȂ�ƁA��C�Ɂu������O�v�̘b���ɂȂ����悤�ȋC�����܂��B
���Ȃ��A�ŏ��ɏ����܂����悤�ɁA���̕i���Ǘ��ɂ��Ă͑�ςɏd�v�ł���A��������̂�������e�ł��邽�߁A�u�P�A�v�������ʍu���v�Ő������܂��B
�Q�D���T�[�r�X�ɂ�����i���Ǘ����s�Ȃ����߂̃|�C���g
�@�i���̕��j�y�іڕW��O��i���m���j���邱��
���悸�́A������T�[�r�X�̓��e��A���Ɨʓ��B������₷�������A�����̂Ƃ���i�{�݂⎖�Ə����j�Œł��郌�x����A���j�������߂邱�Ƃł��B���̃��x���ȉ��ɂ͐�ɂ��Ȃ��Ƃ�����̓I�ȑ̐��Â��肪�d�v�ł��B
���{�݂⎖�Ə��Ƃ��āA�o�c�҂Ƃ��Ắu���z�v��u���O�v�͂���߂ďd�v�ł��B���̗��z�◝�O���������邽�߂̖��m�ȕ��j�ƁA�����\�ȖڕW�����肷�邱�Ƃł��B���z�◝�O�������f���Ă������͓���ƌ����܂��B
�����̕��j��ڕW��O�ꂷ�邽�߂ɂ́A���������邱�Ƃ��d�v�ł����A�`�F�b�N�@�\���܂߂��̐��i�g�D�j���A�����Č�Ő�������Ɩ��̕W�������K�v�ƂȂ�܂��B
���܂�A�Ⴆ�u���p�Җ{�ʂ̐����S�ʂ��x������T�[�r�X����邱�Ɓv�Ƃ������z�����ł́A���ۂɉ��T�[�r�X�������X�́u�S�l�\�F�v�̍l�����ƕ��@�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�A�i���̏�����͂��K�ɑΉ���\�h�����邱��
�������ł͑傫��������ƂQ�|�C���g������܂��B�悸�́A�i���̏�����͂��邱�Ƃ̏d�v���ł��B
���i�����Ǘ�����Ƃ����Ă��A���f��`�F�b�N��������W�ς��Ȃ����Ƃɂ́u�o���Ɗ��v�̐��E�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����āA�f�[�^�͏W�ς���̂��ړI�ł͂Ȃ��A��������p����A�܂��͂��Ė𗧂Ă邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł��B�u�f�[�^�̂��߂̃f�[�^�v�u�L�^�̂��߂̋L�^�v�����ł́A���ԁi�J�́j�̖��ʂɂȂ��Ă��܂��܂��B
���܂��A�����ƌ����Ή�͂��邽�߂̃f�[�^���Ƃ�邩�ǂ��������Â��܂��B
�����ɁA�K�ȑΉ���\�h���s�Ȃ����Ƃł��B���ɉ��T�[�r�X�ɂ����ẮA�T�[�r�X�Ƃ��������ɉ����A��含���v������܂��̂ŁA���̗\�h���邱�Ƃ̏d�v���͂���߂č����Ǝv���܂��B
���܂�A�u���v�Ȃ��蒼�����ł��܂����A���T�[�r�X�́u��蒼���v�������Ȃ��̂ł��B
���Ȃ��A���T�[�r�X�ɂ����ẮA���p�҂̏̕ω��ƂƂ��ɁA�P�A�v�����Ƃ��̃��j�^�����O�ƕ]�����d�v�ȃf�[�^�ƂȂ�܂��B
�B�i���ɖ�肪����Β����ɑΉ����邱��
����́u�A�i���̏�����͂��K�ɑΉ���\�h�����邱�Ɓv�Ɩ�肪������A�u�����Ɂv�Ή����邱�Ƃł��B
���u����v�u�����v�u��Łv���ł́u���P�̃`�����X�v�������łȂ��A�u���z�̃X�^�[�g�v�ƂȂ��Ă��܂��댯��������܂��B
�C�K�Ȓ̊���̐����m�ۂ��邱��
�����̂��Ƃɂ��ẮA�ŏ��́u�@�i���̕��j�y�іڕW��O��i���m���j���邱�Ɓv��A�O��́u�y�X�z�s�K�ȉ��T�[�r�X����Ȃ����߂ɂ́v�ł����������悤�ɁA�ƂĂ��d�v�ł���A�܂��ł����Ԃ��w�͂��K�v�ƂȂ�܂��B
���������A�u�p���͗͂Ȃ�v�Ƃ������t������܂����A�p����������Ηǂ��킯�ł͂Ȃ��ł�����A�����̂Ƃꂽ�v��I�Ȋ���̐��Â���̌p�����u�́v�ƂȂ�ƍl����ׂ��ł��B
�D�̌n�I�Ōp���I�ȋ�������{���邱��
�����݂̑����̌��C�́A���Ɍ����u�P���v�̌��C�ł���A�u�K�n�v���čs���ɂ͓�����ɂ���܂��B
�����͍���A���x�������̕��X�Ɋւ��Ă̌��C�����x�����Ƃɍו�������Ǝv���܂��B�Ⴆ�A���C�ґΏۂ̌��C���C�ƒ����҈ȏ�̐�匤�C�B�����čX�Ƀ��[�_�[���C��X�[�p�[�o�C�U�[���C���ł��B
���������A����͎��Ԃ�������܂��B���͂��́u�g�g�݁v�����i�K�ŁA���セ�̃e�L�X�g�⌤�C���@�̎��s���낪�s�Ȃ��܂����A���ۂɎn�܂��Ă��܂��B
����������ŁA���C�̐��ʂ́A�u�đ��v�ɂ���đ傫�����E����܂��B���́u�^������v���̂ł͂Ȃ��A�u�w�͂��Ē͂ݎ��v���̂��Ƃ����ӎ����v���K�v�ł��B
�E�Ɩ�����W�������邱��
�����x�������̋Ɩ��͕W��������Ă���ł��傤���B���t�Ǘ��Ɩ��͕W��������Ă���ł��傤���B
����́u�C�K�Ȓ̊���̐����m�ۂ��邱�Ɓv��u�D�̌n�I�Ōp���I�ȋ�������{���邱�Ɓv�Ƒ��݂ɊW���Ȃ���Ɩ��̕W�������m������čs���̂ł��傤�B
���Ɩ����W�����ł��Ă��Ȃ��ł́A�̐������A���C���A�����ĕ]������ł��Ȃ��킯�ł�����A���̋Ɩ��̕W�����͍ŗD��Ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B
�F�T�[�r�X�҂̃��`�x�[�V�������ێ��E���コ���邱��
�����Ƃ̂��Ƃ��ł��d�v�ŁA���݁A��쌻��̕��X�̐؎��ȔY�݂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����P��̉��x�������̎����̎��Ɏv���`���Ă������z�ƌ����̃M���b�v�B���t�Ǘ��Ɩ�����Ɩ��Ƃ������ώG�Ȏ�����Ƃ̘A���B�p�\�R���Ƃ́u�ɂ߂����v�E�E�E�B
�������āA�u�R���s���nj�Q�v��A���ɖ����Ă��܂����B����I�ȉ����̕��@�͂���܂���B�����ł��A���S�ɕԂ�A���Ԃ����A�C���炵�̎�������E�E�E�B
�������������ƂɁA���́u�P�A�v�����̍L��v�������ł������ɗ��Ă�Ɛؖ]���A������X�Ȃ���e�̏[���ɓw�͂��čs���܂��B�����āA�ꏏ�Ɋ撣��܂��傤�B
��2002�N 1�� 3���f�ځ�