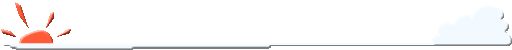
【11】初回面接のポイント①(バイスティックの7原則)について
1.初回面接(インテーク)の重要性
●ケアマネジメントの「入り口」である初回面接(インテーク)は、利用者や家族の要望等を聞きとる最初の面接として大変に重要な過程となります。
●私の経験上からも、この初回面接で「その後の展開が決まる」と言っても過言ではないと思います。
●保健・医療・福祉の専門家としての介護支援専門員であっても、利用者や家族にとっては「全くの他人」「第三者」であることには違いがありません。
●利用者や家族が、その「全くの他人」に現在の生活上で困っていることや、家族関係などのプライバシーまでも相談(話す)して、「第三者」から「担当のケアマネジャー」、「信頼する専門家」、そして介護保険制度の「水先案内人」と変わる「劇的瞬間」とも言えます。
●面接を行なう介護支援専門員の心構えや態度として、初回の面接を「事務的に処理」すれば、その後の両者の関係も事務的な関係と「事務作業」となってしまうでしょう。
●また、介護支援専門員の面接技術や洞察力、専門的知識によって、利用者の真のニーズや援助の方向性が、スタートからズレを生じる危険性もあり、その後のアセスメント、介護サービス計画にも大きく影響を及ぼします。
●と言うより、利用者や家族、そして介護支援専門員の両者の最初の「印象」や「考え(意向)」は、思う以上に影響力が大きいのではないでしょうか。
●そこで、今回は「バイスティックの7原則」を例にし、ケースワーク、対人援助技術の基本原理・原則の重要性を再認識すると同時に、現場で実現することの難しさについても説明をします。
2.バイスティックの7原則
①個別化の原則
●個別化ということは、ケースワーク、対人援助技術だけでなく、ケアマネジメント、ケアプラン、そして人間関係の基本でもあります。
●しかし、多くの事例を経験してベテランとなって行くときに、自分自身でも注意しないと、この個別化の原則を見失うことがあります。
●つまり、初回面接時に、「寝たきりの高齢者のケース」「痴呆症状のある高齢者のケース」「独居のケース」「同居のケース」、あるいは「訪問介護(看護)利用のケース」「通所介護(リハビリテーション)サービス利用のケース」等、個別化ではなく「パターン化」してイメージしてしまう傾向が強くなるということです。
●もちろん、そのイメージをする事自体は経験が成せる「技」であり、悪いことではないと思います。
●ただ、そのパターン化されたイメージの中での「そのケースの個別性や特殊性」までを描ききれずに、対応や思考も「流れ作業」になることの危険性は回避しなければならないのではないでしょうか。
②自己決定の原則
●介護支援専門員の方々の研修などで、「利用者と家族の意向が違う時はどちらを優先するべきか」、あるいは「利用者や家族の意向と、課題分析(アセスメント)によって判断される介護支援専門員がとらえるニーズのどちらを優先すべきか」等の質問を多く受けます。
●この疑問(質問)自体の答えが、この「自己決定の原則」です。
●しかし、この原則の真意は「自己決定と自己責任」、つまり「権利と責任」の関係での原則です。
●単純に、利用者や家族の意向だけでケアプランを作成するのであれば、それは「利用者によるケアプランの自己作成」と同じであり、「責任」を全て利用者と家族が担うことになります。
●利用者や家族に、介護サービス利用の効果(成果)や、利用者の今後の状況変化の予測等の専門家としての判断を分かり易く説明(情報提供)した上で、最終的に決定するのが利用者であるということだと思います。
③受容の原則
●利用者の全てを受け入れ、全人格として尊重することの原則ですが、介護支援専門員という専門家であっても神様ではありません。
●職場やプライベートな環境を改善し、ストレスのない状態にすることも大切な仕事です。
●利用者や家族との「相性」も現実にはあります。「相性」が合わない場合は、担当を変えるということも事業所のチームワークでカバーできる方法です。
●「仕事だから」と、自分自身を無理強いすると、結局はこの原則が高いハードルになってしまいます。
●無理は続きません。
④非審判的態度の原則
●この「非審判的態度の原則」が専門家としては、大変難しいことなのではないでしょうか。
●利用者や家族と、保健・医療・福祉の専門家であり、しかも理解するのが難解な介護保険の運用者である介護支援専門員との間には、知識を含めた圧倒的な情報や判断力の差があります。
●その大きな格差の関係の中で、「非審判的態度の原則」を守ることは何と難しいことでしょうか。
●また、「息子なんだから」「娘なんだから」「嫁なんだから」「家族なんだから」等という発想自体が、「非審判的態度の原則」に反すると思えます。
⑤秘密保持の原則
●このことは、専門家として当然のことですが、「ついウッカリ」という場面は、時々あるようです。
●例えば、「隣のAさんも通所介護を利用される前は、お嫁さんと色々あったようですが、今はAさんも楽しみができたし、お嫁さんも自由な時間ができて、お互いの関係がとても良くなったと聞いています。Aさんと一緒に通所介護を利用しませんか。」という話しは、厳密に考えれば、隣人のAさんの家族関係の秘密保持の原則に反しています。
●また、利用者の特定の名前を言わなくとも、時々、電車の中なので、「あの人は~だから、困っているのよ」等と、介護サービス関係者と思われる方達の話しを聞くことがあります。
●私自身としても、自分の家族が介護サービスを利用していたことがありましたので、「自分の家族のことも、こうやって公衆の面前で話しをされていたのかなあ~。」と、少し悲しくなります。
⑥統制された情緒関与の原則
●この原則は、大変に難しいことです。単に注意したり努力すれば達成できることでもないと思います。
●利用者の感情を、感受性をもって理解し、援助目標にそって適切な情緒的関わりをするということの難しさは、私の経験上からも最も難しい原則です。
●この原則を実現するためには、経験が豊富で優れたスーパーバイザーによる教育が必要だと思います。
●つまり、個々の努力だけでは難しく、体系的な教育によるスーパービジョンが必須です。
●もちろん、定期的な自己チェックと、スーパーバイザーによる他者のチェックが継続的に必要となります。
⑦意図的な感情表現の原則
●利用者が自己の感情を自由に気がねなく自由に表現できるように、意図的に感情を表現するという原則というより具体的な方法です。
●これを「本音で語り合える関係づくり」「仕事を超えた信頼関係づくり」等の方向で考えると、ケースワークやケアマネジメント等での両者の関係を逸脱し、利用者や家族が介護支援専門員の方々に「依存的」になったり、逆に「そんなつもりじゃなかったのに」等と、歯車がズレ始めると「感情的な亀裂や拒絶」へと発展し、修復が困難となる危険性の方が高くなると思います。
●この原則についても、上記の「⑥統制された情緒関与の原則」と同様に、スーパービジョンによる教育が必要で、自己及び他者のチェックがないと「意図的」ではなく「独善的」な感情表現となってしまう恐れがあります。
<2002年 1月29日掲載>